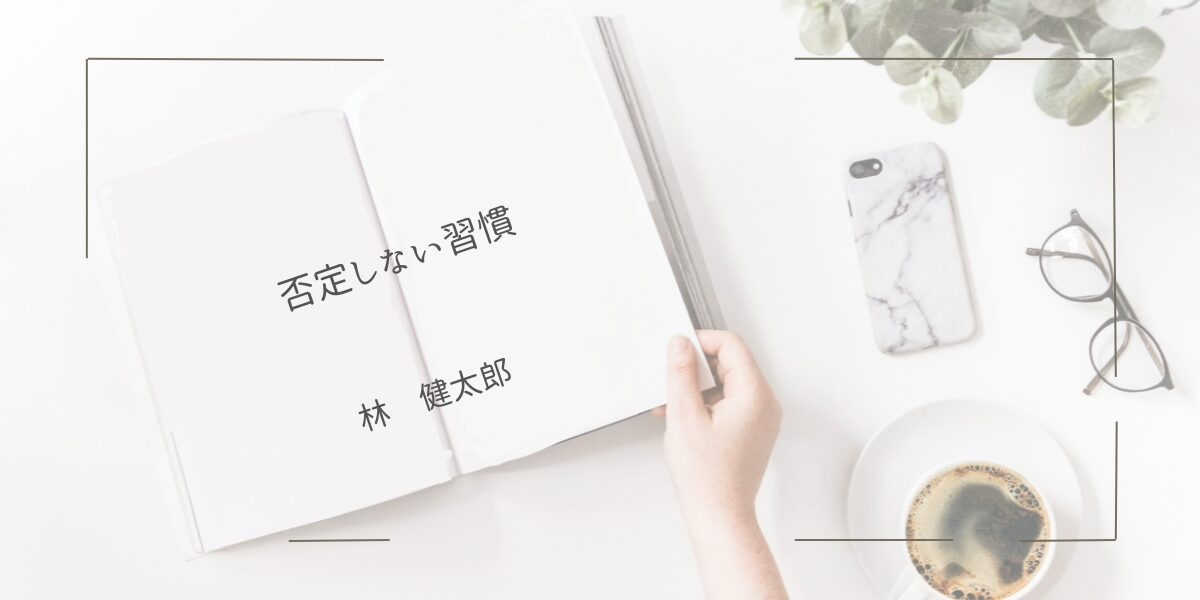みなさん、パートナーや後輩、友人などになんでそんなに「否定」するの?と言われた経験はありますか。
恥ずかしいですが、私にはあります。
妻と付き合い始めてから、言い合いになってしまった時には、毎回のように言われていました。
最近でもたまに言われることもあり、自分では否定してるつもりは全くないのになんでこんなに言われるんだ?と自分自身が嫌になることが多々ありました。
そんな自分を直したいとずっと悩んでいた時に本書「否定しない習慣」を見つけました。
読めば読むほど、今までの自分にグサグサと刺さり、自分の直すべき部分を見つけ出すことができ、意識しながら生活をすることができるようになりました。
パートナーとの関係だけでなく、子育てや、会社での人間関係にも使える技術、習慣を学ぶことができる本です。
本の基本情報、概要
著者
林 健太郎(はやし けんたろう)
リーダー育成家。合同会社ナンバーツー エグゼティブ・コーチ。一般社団法人 国際
概要
仕事やプライベートでの人間関係を劇的に良い関係にする為の方法が詰まった一冊。
「肯定する」「褒める」などが人間関係をよくするのに良く言われるいい方法ですが、最も効果的かつ、劇的に人間関係を変えるには「否定しない」ということ。
この本では「否定しない」の技術やマインド、習慣化にするには?を学ぶことができます。
本書で得た「気付き」
「否定されない」とどうなるのか?
人間は「否定ばかりされる」と
- 怒りが生まれる
- オープンに話せなくなる
- 信頼関係が生まれにくくなる
- 自己肯定感が低下し、自信を持てなくなる
逆に「否定されない」と
- ポジティブな感情になる
- もっとコミュニケーションを取りたくなる
- 信頼関係が生まれる
- 自己肯定感が高まり、自信が持てる
というシンプルな「事実」がある。
実際私にも経験があり、否定ばかりする人とはあまり話したくなくなり、必要最低限のことしか話さないようになりました。
相手の話が終わってからの2カウント
大原則として、「相手が話し終わるまで黙ったまま」でいる。
何度も話をさえぎりたくなるかもしれないが、我慢する。
相手の話をさえぎってしまったら、話をさえぎった時点でそれはもう、立派な「否定」になってしまう。
それができたら、次のステップとして、相手が言いたいことを話し終わったなと思ったら、そこから最低約2秒は沈黙をし続ける。
ずっと我慢していると、食い気味に発言してしまい、その言葉は否定になりやすいので、自分自身の冷却時間が約2秒必要。
一瞬でも意識的に思考を巡らせる時間があることが大事で、この数秒の沈黙で自分の感情を抑えることが大切。
相手に違和感を持たれるくらいでちょうど良く、「否定して嫌われる」よりも「沈黙して平和な関係性を保つ」ほうが賢い選択。
「非言語」を整えて否定を消す方法
人間は言語に限らず、非言語からもたくさんの情報を得ている。それどころか、「非言語コミュニケーションによる影響の方が、言葉によるコミュニケーションより大きい」という研究すらもある。
いくら否定的な言葉を使っていなくても、態度で相手を否定していたら全てが台無し。全部相手に伝わっている。
具体的に否定を表す非言語とは…
- 眉間にしわを寄せる
- 口をへの字にする
- 腕を組む
- 足を組む
- 貧乏ゆすりをする
- 腕時計やスマホを見る
などです。特に最後の2つは否定というよりも「あなたの話はもう聞きたくないよ」と伝える態度で、これらの態度は否定的な心をダダ漏れさせてしまう。
コミュニケーションでは「何を言っているか」以上に「相手にどう見えているか」が重要。
逆に、否定しない「肯定的な非言語」の中で特に重要なのは笑顔。
本書はKindle Unlimitedで無料で読むことができる?
残念ながら「否定しない習慣」はKindle Unlimitedで無料で読むことはできませんでした。
しかし、Kindle Unlimitedなら月額980円で数千冊の本が読み放題です!
月に1冊本を読めばペイできちゃいます。
初回30日間無料体験ができるのでまずは試してみてください!
Kindle Unlimited無料体験リンクまとめ
今回は、林健太郎さんの「否定しない習慣」のブックレビューをしてみました。
読み進めていけば行くほどに「否定ばかりするよね」と言われていた自分の心にグサッと刺さる内容で、とても勉強になると同時に今までをとても反省して、見直すことができました。
恥ずかしい話ですが、本書を読んでから、妻と話し合う機会があったのですが、「否定しないで話せるようになったね」とびっくりされました。笑
そのくらい今までは否定ばかりしていたんだなと反省しました。
聞く態度や話し方を少し変えるだけで、かなりの効果を実感することができると思います。
パートナーとの関係だけではなく、子育てや、会社での後輩、部下の育成や人間関係にもかなり効果があると思うので、全ての人におすすめの本です。
他にもブックレビューや子育てについて、趣味などの記事を書いています!ぜひ合わせて読んでみてください。